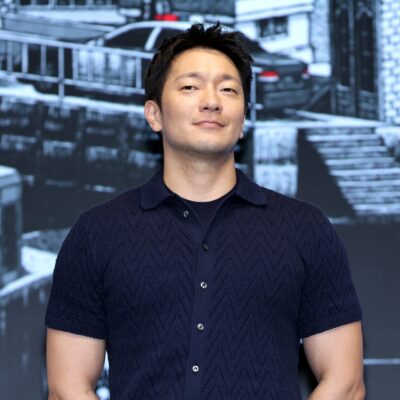09.11
後退するアメリカーー米中首脳電話会談で「一つの中国」を認め、ウイグル問題を避けたバイデン
9月9日、バイデンは習近平に電話を掛けて「衝突を避けたい」旨の意向を伝えたと日本では報道されているが、バイデンは本当は何と言ったのか、何を言わなかったのか。米中双方の公式報道から読み解く。 日本での報道 日本での報道は、たとえば9月10日の時事通信社の「衝突回避で双方に責任 中国主席と電話会談 米大統領」などが一般的で、【ワシントン、北京時事】という米中双方の情報から書かれているので読み解きやすい。 それによれば、ホワイトハウスは、米中間の競争を紛争に転じさせないための「両国の責任」について議論し、両首脳は利益が重なる分野と、利益や価値観、視点の異なる分野について「広範な戦略的議論」を行ったとのこと。また、バイデンは習近平に対し、インド太平洋地域と世界の平和や安定、繁栄に関する米国の揺るぎない利益を強調したともある。 一方、中国共産党機関紙・人民日報(電子版)によると、習近平は「一時期から米国が取る対中政策は中米関係に著しい困難をもたらした。これは両国民の根本的利益や世界各国の共通利益に合致しない」と批判したとある。その上で、「中米関係を安定的発展という正しい軌道に早く戻すべきだ」と訴え、気候変動、新型コロナ、経済回復、「重大な国際・地域問題」の各分野で協力を呼び掛けた。 以上が概ねの日本の報道だ。 中国における公式報道 中国側の正式報道は、中国の外交部にある「習近平がアメリカ大統領を電話会談した」が最も信憑性が高い。これが間違っていればアメリカから直ちに修正が求められる。今のところそのような動きはないので、間違っていないものと解釈することができる。 では、習近平は何を言ったかを先ず見てみよう。 習近平: 1.(8月29日にルイジアナ州で起きた)ハリケーン「アイーダ」に関するお見舞いの言葉を述べた(バイデンは謝意を表した)。 2.ある時期以来、アメリカの対中政策は中米関係に深刻な困難をもたらしており、これは両国人民の根本的な利益と世界各国の共同利益に反する。 3.中国は最大の発展途上国で、アメリカは最大の先進国だ。したがって中米両国が互いの関係をうまく処理できるか否かは、世界の未来と命運を左右する大きな問題であり、両国が良い解答を出さなければならない世紀の問題である。中米が協力すれば、両国と世界は利益を得ることができる。中米が対抗すれば、両国と世界はともに苦しむことになる。米中関係は、「正しいかどうか」という多肢選択式の問題ではなく、「どうすれば正しいか」という必答式の問題だ(筆者注:最後の言葉は分かりにくいが、西側諸国には対中包囲網を呼びかけながら習近平に対しては「きれいごとを言う」バイデン政権に対する習近平の不満を表していると解釈できる)。 ===== 4.古詩曰(いわ)く「山重水複疑無路 柳暗花明又一村(山が幾重にも重なり、川もうねうねと曲がりくねって、この先は行き止まりかと思いきや、薄暗く生い茂った柳の向こうに、色鮮やかな桃の花に囲まれた村があった)」。このように、中米は1971年に二国間関係の「氷」を破って以来、協力し合い、各国に具体的な利益をもたらしてきた。現在、国際社会は多くの共通の難題に直面している。中米は大局的な見地に立ち、大きな責任を担い、しっかり前に向かって進み、戦略的な大胆さと政治的な勇気を示して、中米関係が安定した発展の正しい軌道に一刻も早く戻るように促進し、両国民と世界各国の人々に貢献しなければならない。 5.(気候変動・コロナ・経済回復…などの問題に触れた後)より多くの協力の可能性を見つけ出し、引き続き対話を行い、両国関係にさらなる肯定的な要素を加えていく必要がある。 それに対してバイデンは以下のように応じた。 バイデン: 一、世界は急速な変化を遂げており、米中関係は世界で最も重要な二国間関係だ。米中がどのように相互作用するかは、世界に大きな影響を与える。 二、米中両国が競争のために対立し衝突に陥るなどという、いかなる理由も(必要性も)ない。 三、アメリカは一度も「一つの中国」政策を変えようと思ったことはない。 四、アメリカは中国と、より率直な交流と建設的な対話を行いたいと心から望んでいる。双方が協力できるような重点事項や優先領域を特定し、誤解や誤判断あるいは予想外の衝突を避け、米中関係を正しい軌道へと戻したいと強く願っている。 五、気候変動などの重要な問題について中国とのコミュニケーションと協力を強化し、より多くの合意を得られることを期待している。 アメリカにおける公式報道 アメリカはホワイトハウスのブリーフィングルームが、9月9日、”Readout of President Joseph R. Biden Jr. Call with President Xi Jinping of the People’s Republic of China”(ジョセフ・R・バイデン・ジュニア大統領と中華人民共和国の習近平国家主席との電話会談について) をリリースした。 そこには以下のように書いてある。 ===== ――ジョセフ・R・バイデン・ジュニア大統領は、本日、中華人民共和国の習近平国家主席と会談しました。両首脳は、広範かつ戦略的な議論を行い、我々の利益が一致する分野と、我々の利益・価値観・視点が異なる分野について議論しました。両首脳は、この2つの問題について、オープンで率直に取り組むことに合意しました。バイデン大統領が明らかにしたところによれば、この話し合いは米中の競争を、責任を持って管理するためにアメリカが進めている取り組みの一環である。 バイデン大統領は、インド太平洋および世界の平和・安定・繁栄に対する米国の永続性のある(辛抱強い)関心を強調し、両首脳は、競争が紛争に発展しないようにするための両国の責任について議論した。 バイデンは「一つの中国」原則を守ることを誓っている 米中両国の公式報道を見ると、ずいぶんと大きな違いがあることにお気づきだろう。 われわれ日本人にとって最も大きな関心があるのは「台湾の位置づけ」だ。 しかし中国側発表の「三」にあるように、バイデンは習近平に対して、「アメリカは”一つの中国”原則を守ります」と誓ったことになる。 「一つの中国」原則を守るということは、この世に「中国」を代表する国家としては「中華人民共和国」しかなく、「台湾」は国家ではなくて、あくまでも「中華人民共和国の領土の一部に過ぎない」という位置づけになる。したがって中国が台湾をどのような形で「統一」しようとも、「他国」は「内政干渉はしません」ということを誓ったと同じことになるのである。 香港のように「一国二制度」を1997年の中国返還から50年間は保ちますよと関係国に誓ったというような条件や縛りはない。 事実上、1971年にアメリカが「中国」の代表として「中華人民共和国」を選び、当時の「中華民国」(現在の台湾)とは国交断絶して切り捨てるという道を率先して選んだだけのことだ。その結果「中華民国」は国連を脱退して「台湾」と呼ばれなければならなくなった。 上記の「三」で示したバイデンの言葉<アメリカは一度も「一つの中国」政策を変えようと思ったことはない>は、中国が台湾に何をしようと、それは中国の自由で、アメリカが何か言うのは「内政干渉に相当します」と認めたことを意味するのである。 そのような大前提の下に、対中包囲網など形成できるはずもなく、バイデン政権の対中弱腰姿勢が透けて見える。 事実、今年2月8日のコラム<バイデン政権の本音か? 米中電話会談、「一つの中国」原則に関する米中発表の食い違い>に書いたように、2月5日にブリンケン米国務長官が中国の楊潔チ・外交トップと電話会談した時に、ブリンケンは明確に「米中関係は両国および世界にとって非常に重要だ。アメリカは中国とともに(協力しながら)安定的で建設的な両国関係を発展させていきたい」とした上で、「アメリカは今後も『一つの中国』政策を引き続き推し進めていき、かつ三つのコミュニケを必ず遵守していく。この政策に関するアメリカの立場は変わっていない」と繰り返し述べている。 ===== また2月12日のコラム<米中首脳電話会談を読み解く――なぜ「とっておきの」春節大晦日に?>に書いたように、今年の春節大晦日に習近平と電話会談したバイデンは「中国は悠久の歴史を持つ偉大なる文明の国家であり、中国人民は偉大なる人民である。米中両国は衝突を避けなければならない」とした上で、「アメリカは喜んで中国とともに、相互尊重の精神に基づき、率直で建設的な対話を続け、誤解や誤判断を避けるべく相互理解を深めていく」と言っている。 だから、どんなに日本などの同盟国に呼び掛けて対中包囲網を形成しようとなどしても、言行不一致で信用できないのである。 後退するアメリカ――今回はウイグル・香港問題などに言及していない 前述の<バイデン政権の本音か? 米中電話会談、「一つの中国」原則に関する米中発表の食い違い>に書いたように、ブリンケンは今年2月5日の電話会談のときには、明確に中国側に対して「新疆ウイグル自治区やチベット自治区および香港を含めて、アメリカは人権問題と民主的価値を支持し続ける」と強調している。 同様にバイデンは前述のコラム<米中首脳電話会談を読み解く――なぜ「とっておきの」春節大晦日に?>に書いたように、バイデンは「北京政府の強圧的で不公正な経済慣行、香港での取り締まり、新疆ウイグル自治区での人権侵害、台湾を含む地域でのますます強まる独断的な行動について強い懸念を抱いている」と強調している。 しかし今回はウイグル問題も香港問題も口にしておらず、明らかに対中姿勢としては後退していることが見て取れる。 これは「もし可能なら10月に開催されるG20では会ってね」というお願いのためであり、もう一つはアフガニスタンにおける米軍撤退の失敗を言われたくないからだろう。 なんとも情けないではないか。 このような状況の中で、もし日本の次期自民党総裁が(内心)親中派であり、次期衆院選で自公が勝って野党が負けるとすれば、日本は親中派の人物が首相となることになり、米中総崩れになる危険性を孕んでいるのではないかと憂う。 もっとも、野党の対中姿勢を聞いたことがないので、衆院選までには明示してほしいと思ってはいるが…。 追記:冒頭の時事通信社の記事は、その後、内容もURLも変更したらしく、リンク先の記事が無くなっている。元のままにする。 ※当記事はYahoo!ニュース 個人からの転載です。 ≪この筆者の記事一覧はこちら≫ [執筆者]遠藤 誉 中国問題グローバル研究所所長、筑波大学名誉教授、理学博士 1941年中国生まれ。中国革命戦を経験し1953年に日本帰国。中国問題グローバル研究所所長。筑波大学名誉教授、理学博士。中国社会科学院社会学研究所客員研究員・教授などを歴任。著書に『裏切りと陰謀の中国共産党建党100年秘史 習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』(ビジネス社、3月22日出版)、『ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元』、『激突!遠藤vs田原 日中と習近平国賓』、『米中貿易戦争の裏側 東アジアの地殻変動を読み解く』,『「中国製造2025」の衝撃 習近平はいま何を目論んでいるのか』、『毛沢東 日本軍と共謀した男』、『卡子(チャーズ) 中国建国の残火』、『ネット大国中国 言論をめぐる攻防』、『中国がシリコンバレーとつながるとき』など多数。
Source:Newsweek
後退するアメリカーー米中首脳電話会談で「一つの中国」を認め、ウイグル問題を避けたバイデン