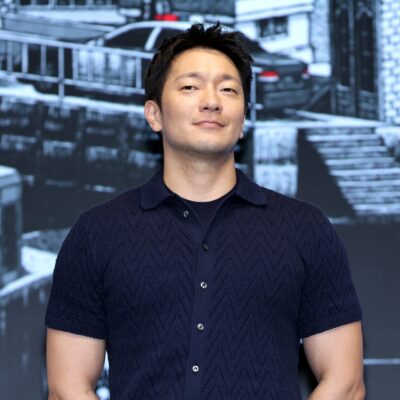08.23
ドングリキツツキの新たな生態が判明 一夫多妻制で繁殖を有利に
<枯れ木に食料を貯め込むドングリキツツキに、新たな個性が判明した> ヒトの世界を見るかぎり、一夫多妻制を敷く文化は限られているかもしれない。ところが一部の鳥類においては、種全体の子孫繁栄を助けているようだ。ドングリキツツキと呼ばれるめずらしい習性をもったキツツキについて、アメリカの研究者たちが解き明かした。 北米などに分布するドングリキツツキは、越冬のために計画的にドングリを蓄えるというめずらしい行動で知られる。立ち枯れた木や木製の電柱などを見つけては、ときに1万個を超える膨大な数の穴を開け、穴の一つひとつにドングリの実を貯蔵する。(鳥の名で検索すると写真が多くヒットするが、集合体恐怖症の方はご注意を。) 雨の日が増え好物の虫が飛ばない冬季になると、こうして用意したドングリいっぱいの枯れ木は、日々を生き抜くための貴重なエネルギー源となる。 ユニークな習性をもつこの鳥について、このたび繁殖という面で新たな発見があった。多数のメスを相手にするオスの方が、繁殖を行える年数が延び、生涯で残せるヒナの数が増えるのだという。 40年にわたる研究で解明 ドングリキツツキのオスには、特定のメスを選び1対1のペアで営巣する個体と、1つの巣に複数のメスを迎える個体とがある。アメリカの生態学者たちが調査したところ、複数のメスを相手にする個体の方が生殖を有利に運んでいることがわかった。 研究の結果、「一夫多妻制」で営巣する場合、営巣1回あたりの産卵数は低下することが確認された。しかし、生殖可能な期間が2〜3年延びることで営巣回数が増え、生涯全体としては純粋なペアで営巣するオスに比べ、1.5倍の数のヒナを設けていることが判明した。 メスについても生殖可能な期間がやや延び、生涯全体では一夫多妻制の方が有利とまではいえないものの、ペアでの営巣と同水準の数のヒナを設けている。 研究論文は米スミソニアン博物館群の一角、国立自然史博物館で館長を務めるサハス・バーヴ生態進化生物学博士らのチームが著し、学術誌『英国王立協会紀要』に掲載された。 鳥類の生態を正確に把握するためには、非常に多数のサンプルと長期にわたる観察が求められる。バーヴ博士たちはカリフォルニア州にある広大なヘイスティングス自然歴史保護区において、40年にわたるデータ収集を行なった。個々の鳥を識別することは困難を極めたため、小型の無線機をハーネスで背中に背負わせることで位置を追跡した。さらに499羽から遺伝子サンプルを採取することで、研究に必要なデータを収集したという。 バーヴ博士は米スミソニアン誌に対し、「(研究結果は)長期に及ぶ動物行動学上の研究の貴重さを物語るものです」と述べ、40年にわたる記録の結実を喜んでいる。博士はまた、自然淘汰のメカニズムは多くの種に共通するものだとも述べ、本研究がキツツキに限らず他の動物の行動にも役立つ可能性があるのではないかと期待している。 ===== 兄弟・姉妹が子育てをお手伝い 一夫多妻制以外にもドングリキツツキは、兄弟姉妹が育児に参加するというめずらしい習性で知られている。最大16羽ほどの成鳥が集団でヒナの世話をし、育ったヒナも数年ほど巣に留まる。次の世代として生まれてきた若いヒナの世話をし、育ててから巣立ってゆくのだ。 これに対し自然界の多くの生物は一夫一婦制を取り、営巣や子育てに関しても各ペアが独立して行う。ドングリキツツキのような社会生活は例外的であることから、自然界から淘汰されつつあるのではないかとの考えが生物学界では一般的だった。 バーヴ博士はこうした見解に対し、実は親族の子育てを手助けする行為にも、進化上のメリットがあるのだと説明している。進化学上有利とされる基準のひとつに、いかに集団の遺伝子のなかに自分のDNAをより多く広めることできるか、という観点がある。この観点において、たとえば自分の4分の1の血を引く甥っ子を2羽育てることは、自分の2分の1の血を引く実の子を1羽育てることと等しい意義をもつのだ、と博士は説く。 さらに博士によると、集団での育成により生存率が向上するなど、種全体に遅効性のメリットが発生しているのだという。 既存の考え方においては、親族の子育てを手伝うことは、自身で子孫を残すことができない場合の最後の手段だと捉えられてきた。積極的に共同で営巣するドングリキツツキの習性は、こうした常識とは異なる新たな価値観を提唱するものとなりそうだ。 高い社会性の反面、凶暴な一面も 以上のように共同で子育てにあたるドングリキツツキは、高い社会性を備えた鳥だといえるだろう。一方、コミュニティの支配をめぐり、異常なまでの闘争心をむき出しにすることもある。 通常は2羽から16羽ほどのコミュニティで生活するドングリキツツキだが、ときに何らかの事情で、グループに属する成鳥のオスまたはメスのすべてが死んでしまうことがある。残された繁殖可能なメスまたはオスをめぐり、複数のグループが激しい争いを繰り広げる。 闘いは熾烈そのものだ。加勢した鳥たちは翼を折られ、地面へ墜ちてしまうこともめずらしくない。目をえぐり取られたり、最悪の場合には怪我によって命を落としたりすることもある。米科学技術誌の『ポピュラー・サイエンス』は、ときに40羽もの鳥が争いに加わり、最大で1日10時間、連続4日間ほど血みどろの戦いを展開すると解説している。元のグループは勝ち抜いた集団を受け入れ、新たなコミュニティとして繁殖活動を再開する。 こうした高い戦闘力と優れた社会性をもつドングリキツツキだが、ときに微笑ましい一面を見せることもある。ニューヨーク・タイムズ紙は昨年、うっかり巣を手薄にしてしまうという習性を明かしている。激しい戦闘が発生すると遠くのテリトリーからもドングリキツツキたちが偵察あるいは野次馬に現れるが、移動に大量のエネルギーを消費するうえ、自分たちの本来の巣が手薄となる。争いを見物しているうちに、せっかく蓄えたドングリを奪われてしまうこともあるのだという。 ドングリキツツキは、北アメリカおよび中央アメリカに分布する。計画的な貯蔵にコミュニティ単位での育児にと、さまざまな表情を見せてくれる野鳥だ。 ===== Woodpeckers vs. the World | National Geographic
Source:Newsweek
ドングリキツツキの新たな生態が判明 一夫多妻制で繁殖を有利に