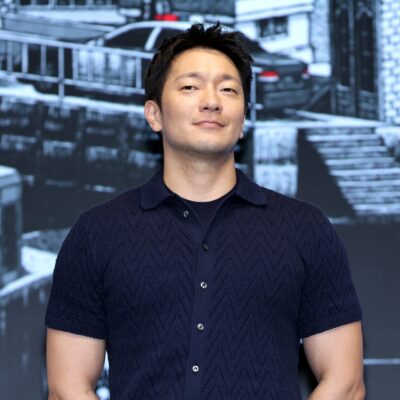07.01
前世代の先輩たちがいつの間にか姿を消していった──氷河期世代と世代論
<急速な世代交代により、長い間「若手」を担ってきた「氷河期世代」も社会の中核となりつつある。「ただ世代交代だけが新しい思想をもたらす」と池内恵・東京大学教授は述べる。論壇誌「アステイオン」94号は「再び『今、何が問題か』」特集。同特集の論考「歴史としての中東問題」を2回に分けて全文転載する(本記事は第2回)> ※第1回:複合的な周年期である2021年と、「中東中心史観」の現代史 より続く 「ヴィジョナリー」から「ヒストリアン」へ このような平凡な「昔話」による「自分語り」は、できれば避けたかったのだが、しかしやむを得ない。それはここのところ急速な世代交代を、身近なところで感じるからである。「昔話」に含まれるごく当たり前の事実を事実と認識できない世代が育っている。 それと共に、「1973年のオイルショックの年に生まれました」「1979年のソ連のアフガニスタン侵攻の時は小学1年生でした」と申告すれば驚愕するかあるいは鼻先で笑ったであろう先行世代、すなわち20世紀の後半を見届けてきた、これまで膨大に重しのように存在していた上の世代の姿が、視界から急速に見えなくなっている。 2011年の「アラブの春」の頃までは、この上の世代は厳然と存在しており、そういった先輩の世代の語る「中東の紛争」といえば、1950年代―60年代のアルジェリア紛争やスエズ動乱であったりしたものである(1990年代のイスラーム過激派をめぐるアルジェリア内戦やエジプトでのテロですらない)。 考えてみればドゴールは日本で言えば岸信介あたりと同世代であり、ナセルやサダト(1918年生まれ)は、田中角栄と中曽根康弘(1918年生まれ)や宮澤喜一(1919年生まれ)と同年代である。 一般に長命で、年功序列の傾向が強い日本において、この世代の人々がそれほど遠くないつい最近の過去まで現役で、あるいは「ご意見番」として機能してきたのだが、その世代の人々は、両世界大戦の帰結や、民族主義・反植民地主義といった冷戦期の世界史の背景・文脈を、自らが生まれ育った時代のものとして身につけていた。 ===== そのような前提で、冷戦構造の中での「中東問題」を見てきた上の世代の語る中東論には、私が歴史書の中の出来事として読む事象を、同時代に体験してきたという揺るぎのない強みがあると共に、冷戦後の新たな前提や状況を理解しにくくなる、どうしようもない古臭さの両方を感じ取らざるを得なかった。上の世代との頻繁な対話のたびに、尊敬と苛立ちを強く感じたものである。 いつまでも立ち退かないように見えた、どこにでも出てくるように見えたそのような前世代の先輩たちが、2010年代に、私が「アラブの春」と「イスラーム国」に忙殺されて日々を過ごしているうちに、いつの間にか姿を消していった。 代わりに目の前に現れるのは、「一番最初に読んだ中東についての本が、池内さんの『現代アラブの社会思想』です」と言う若手研究者や、「『中東 危機の震源を読む』を雑誌の連載で、本でも愛読していました」と言ってくる新聞記者である。もちろんそのように言ってもらえるのは嬉しいことである。 しかし2点で寂しさがよぎる。1つは、結局は、私は上の世代の中東認識を変えることができなかった、という徒労感である。 かつては冷戦期の枠組みによって規定された中東問題に基づく認識が支配的であった。それに対して、私はポスト冷戦期の現実に基づいて、挑戦した(と、今となってはまとめられてしまう)。その挑戦を上の世代の一部は受けて立ってくれたようにも見えるが結局は受け入れたわけでもなさそうであったし、多くは自らの存在を否定されたかのように拒絶した。 私にとっては、「上の世代には見えていない現実と将来見通し」を誰よりも先に、摩擦を乗り越えて示す「ヴィジョナリー」の役割をもっぱら担っていたと言えよう。 現在、冷戦期の枠組みをそのままに中東問題を語る人々は(大学などで制度的に温存・継承されている場合がないではないが)、一般にはほぼいなくなっている。私の示す中東問題の見方に、以前のような強い反対を受けることは無くなった。 ===== しかしそれは私がかつての中東問題認識を持つ人々を説得して考えを変えさせたからではなく、世代が交代し、人間が入れ替わったからである。若い世代は中東問題の理解のための入り口としてしばしば私の本を手にとるようであり(それを意図して多くの本を出してきたのであるが)、それによって、私の意見に反対しないどころか、むしろ私の意見は当たり前過ぎる平凡な認識であり、つまらない、と感じる人さえも出てきているようだ。 それは私の示す現状認識が受け入れられた結果であるのだから、喜ぶべきではあるが、ある種の「張り合いのなさ」を感じる(贅沢な悩みであるが)。「ヴィジョナリー」が示すヴィジョンにより人々の認識が改まったというよりは、世代が入れ替わり、新たな現実を現実と認識して育つ人々が社会の多数になったことで、私が必死に示そうとした「ヴィジョン」は当たり前の現実の記述となった。 このことは、私にとって無用な反論や批判を受けないという意味では好都合である。しかし「人間が生まれ育った環境によって身につけた思想は変わらず、説得されて考えを変えることはない。ただ世代交代だけが新しい思想をもたらす」というのが真理であるとすれば、書き手としてやや寂しいところがある。 私が同時代としてきた湾岸戦争、9・11事件、さらには「アラブの春」までが、歴史書の中で読む遠い過去の出来事としてしか捉えられない世代が育っていく。しかしこれは時間の当然の流れである。そうであれば、「ポスト冷戦期」がそもそも過去の歴史であるという新たな現実を踏まえて、中東問題を「歴史」として書く時期にきているようだ。 それは、私自身が、書き手として、「他の人が見えていない現実と将来を見通す」ことを目指す「ヴィジョナリー」から、過去を過去として現代の読者に適切に認識させる「ヒストリアン」へと転じないといけない時期にきているということなのだろう。今は私個人にとってその過渡期であり、多分に嫌がられることを承知の「昔話」や、気恥ずかしい「自分語り」がしばし漏れることを、ここはご承服いただきたい。 ===== 「崖」を目の前にして 21世紀初頭の20年は、「団塊の世代」やさらにその上の世代が、時に「老人支配」「老害」といった非難を受けながらも、分厚く社会の中枢に居続けた。その陰で、私のような1973年生まれを人口のピークとする「団塊ジュニア」の世代は、「若手」という扱いを受け続けてきた。 「団塊ジュニア」は、物心ついてからの大半の時間を「失われた30年」の中で過ごし、膨れ上がった同世代人口の中での熾烈な競争に晒されながら、バブル崩壊後の就職難により、就業と昇進の機会が限定された「氷河期世代」の「第一期生」でもある。 私自身、職業人生の大半は、「その場で一番若い人」として振る舞うことが期待される環境であり、30代後半から40代になってもなお「新進気鋭」と呼ばれることが通常であった。ところが近年になって、上の世代が否応のない生物学的制約から、次々に退出していくことで、団塊ジュニア世代が、突如として、社会の舵取りを担う指導層の役割を準備なく負わされようとしている。 数年前に、若い頃から注目されリーダーシップを取り、政治・行政的な要職も歴任された先生とふとしたことで茶飲み話をする機会に恵まれたのだが、その先生は私の顔を見るなり「池内君、気をつけなよ。何十年もずっと『若いね、若いね』と言われ続けていると、突然、上に誰もいなくなって、最年長になるんだ。気づくと崖があってね、先頭に立っているんだよ」と仰った。 私が「その場で一番若い人」の役割を長く務めて、ややくたびれつつある様子を、感じ取って、忠告をいただいたのだろう。 否応のない時間の流れによって突然に眼前に「崖」を見出すようになった後に、何をすればいいのか。私にとっては、中東という、日本にとって見慣れない世界をめぐって展開する国際政治の現在とその先を見通す「ヴィジョナリー」から、「中東をめぐって国際政治が回っていた過去の時代」を最初から見届けてきた「ヒストリアン」に転じるために、細々と準備をしているところである。 これは、私が今現在抱えている個人的な「問題」に過ぎないのだが、そこに多少の世代的な背景や使命も認められるのではないかと思う。 池内恵(Satoshi Ikeuchi) 1973年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。国際日本文化研究センター准教授、アレクサンドリア大学(エジプト)客員教授などを経て、現職。専門はアラブ研究。著書に、『イスラーム世界の論じ方』(中央公論新社、サントリー学芸賞)、『[中東大混迷を解く]サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』『[中東大混迷を解く]シーア派とスンニ派』(ともに新潮社)、『新しい地政学』(共著、東洋経済新報社)など多数。 ※当記事は「アステイオン94」からの転載記事です。 『アステイオン94』 特集「再び『今、何が問題か』」 公益財団法人サントリー文化財団 アステイオン編集委員会 編 CCCメディアハウス (※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)
Source:Newsweek
前世代の先輩たちがいつの間にか姿を消していった──氷河期世代と世代論